🧠 算数の文章題が苦手な子に、プログラミングが効く理由
こんにちは、ハローパソコン教室イオンタウン新船橋校の小林です!
「計算はできるのに、文章題になると急にわからなくなる…」
そんなお子さんの様子に、心あたりはありませんか?
実は、算数の文章題が苦手な子どもには共通する“つまずきポイント”があります。
それは「読み取る力」「順序立てて考える力」、そして「自分で整理する力」。
これらはすべて、“プログラミング的思考”と深く関わっているのです。
🧩 「プログラミング的思考」は文章題と相性がいい
「プログラミング的思考」とは、目の前の問題を
-
小さく分けて
-
順番に並べて
-
組み合わせて考える
という考え方です。
これはまさに、文章題を解く時に必要とされるプロセスと同じ。
たとえば、「りんごが〇個、みかんが△個、合わせていくつ?」という文章題。
これを頭の中だけで整理するのが難しい子もいますが、
プログラミングの授業では、
「最初にA、次にBを足して、答えを出す」
という処理を、順番にブロックを並べて視覚的に組み立てていきます。
これにより、「言葉の問題」が「図で見える問題」に変わるのです。
🏫 実際にどう学べる?教室での取り組み
たとえば、教室で開講している「自考力キッズ」では、
ロボットを組み立て、動かすために手順を考える活動を行います。
「どうやって進む?」「どこで止める?」など、
目的に合わせてステップを考える中で、
自然と“順序立てて考える”習慣が育っていきます。
また、小学生向けの「まなるご」や「プロクラ」では、
Scratchというビジュアル言語を使って、
自分で考えたストーリーやクイズをプログラムで再現します。
「もし〜なら」「〇回くり返す」などの条件分岐や繰り返しの考え方は、
算数だけでなく、国語の論理構成にもつながる力です。

🎮 苦手克服は「楽しい!」から始まる
何より大切なのは、「楽しい!」という気持ちです。
算数の問題は「正解しないといけない」というプレッシャーがありますが、
プログラミングの授業では、正解は一つではありません。
「こうしたらどうなる?」「試してみよう!」という姿勢が歓迎されます。
たとえ最初はうまく動かなくても、
「じゃあ、次はどうしたらいい?」と考える時間こそが、学びの宝庫。
この繰り返しが、
「どうせわからない」から「考えればできるかも」に変えてくれます。
🌱 おわりに:得意のきっかけは、思わぬところに
文章題が苦手な子にとって、
プログラミングは“勉強っぽくない勉強”かもしれません。
でも、遊びながら論理的に考える力を育てることができれば、
気づけば「算数、ちょっとわかってきたかも」と思えるようになることも。
子どもにとって「楽しい」「自分でできた」という成功体験は、
どんな教材よりも大きな自信になります。
もしお子さんが「算数苦手…」と言っていたら、
ぜひ一度、プログラミングの世界にふれさせてみてくださいね。

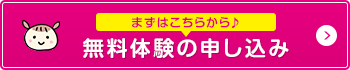
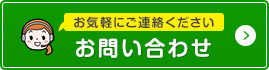
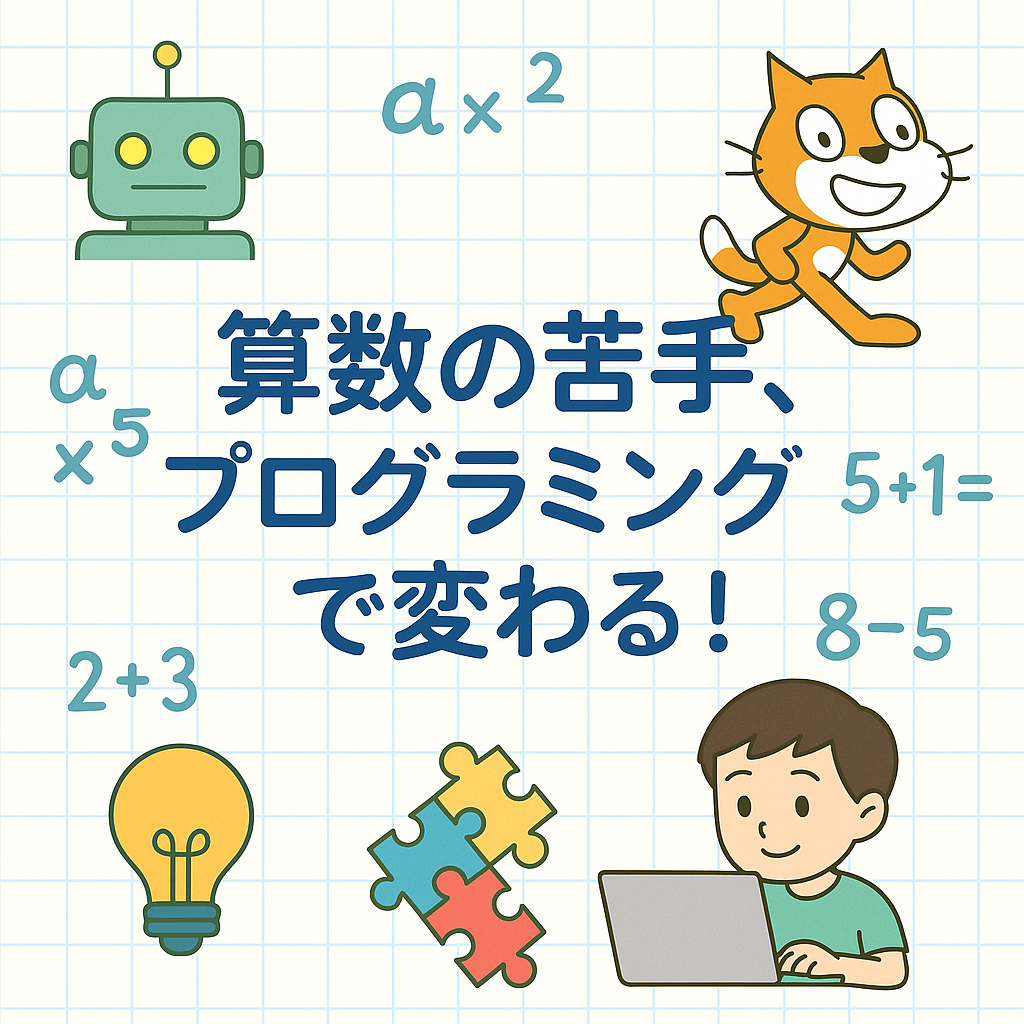
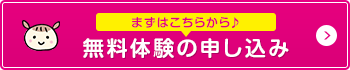


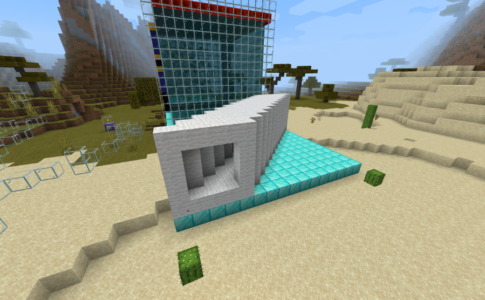
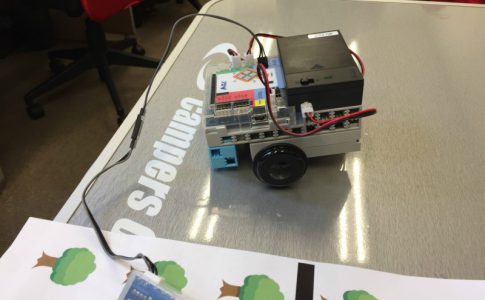

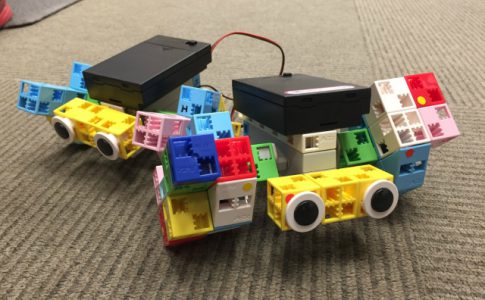
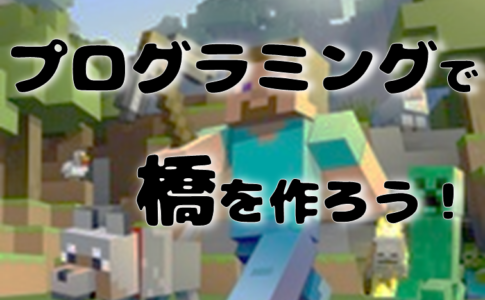
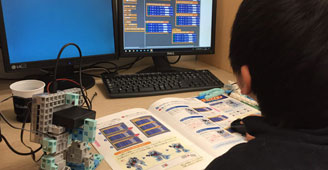

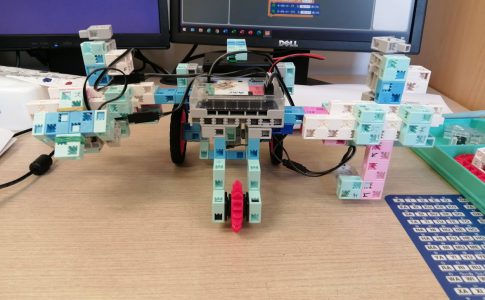
 アクセス
アクセス ページトップ
ページトップ
コメントを残す